でも、周りは新月の夜なのか真っ暗で。
大木の桜が異様な綺麗さを浮き立たせる。
その影によく知る仲間がいた。
桜色が映える浅葱の羽織り。
近寄ろうと駆け出した時。
ざぁ…っ
一陣の風が吹き、木々が揺れ、桜の花片が舞い上がる。
そして、ひとひらひとひら降りてくる花片に合わせて、
一人また一人と暗闇に消えていく。
――待って!
声が届かない。
漆黒の髪が揺れる、一人の男の人が残る。
いつの間にか浅葱の羽織りから、黒の洋装に変わっている。
背に、見慣れた左三つ巴の紋。
ざあ…っ
再び吹く風で視界が薄紅に染まる。
―― さん!
誰かの名前を呼んだ気がした。
静かに、音もなく、舞い上がった花片が降りていく。
もうそこに彼の姿はない。
―― さんっ。
やがて、満開の桜は花片を落とす。
はらはら舞う桜吹雪が、暗闇に溶け込むように消えた。
はらり。
手元に、たったひとひらの桜の花片。
もう桜は咲いていなかった。
何故か、花が終わったばかりだというのに、若葉がない。
―― さんっ!
一人だった。
花がなく、葉もない桜の木の傍。
ひとひらの花片以外、薄紅はなく。
取り残されたように、ぽつんと一人。
周りは暗闇。
―― さん……
必死に誰かの名前を呼んでも、悲しく響き、答えてくれる人はいなかった。
―― さん、行かないで…
膝をつき、崩れる。
ぽたりぽたりと雫が落ちる。
――独りにしないでください…
彼らが消えた先に視線を投げる。
―― さん?
ふと、僅かな残像か、微かにその人を見た気がした。
立ち上がり、追いかけた。
けれど、すぐに風に消えた。
――また、追いて行くのですか…独りにしないで…
呆然と佇む。
―― 。
誰かのよく知る声が響く。
―― さん…っ
もう一度紡いだ名前は、その場に留まり暗闇が吸い込んだ。
「千鶴。」
温かい……何かに包まれているみたい。
これは続き……?
「千鶴。」
誰かが私を呼んでいる。
ゴツゴツした無骨な手が頬に触れて、何かを拭うようにしたあと離れていった。
どこにも行かないで
今度はそっと、頭を優しく撫でられる。
「千鶴。」
今は確かに温もりが傍にある。
苦しいくらい、誰かに抱きしめられているみたいで。
とても温かい。
独りじゃないんだ……
「千鶴。」
もう一度名前を呼ばれた時、千鶴はゆっくりと目を開けた。
その瞳が、心配そうに彼女の顔を覗き込む、菫色の瞳と出会う。
「とし、ぞう…さん?」
まだ夢うつつなのか、千鶴はたどたどしく、菫色の瞳の男の名前を呼んだ。
ひどい夢を見た気がした。
一つ瞬きをすれば、涙が一雫こぼれ落ちた。 それを土方が拭い、そのまま千鶴の背に腕を回した。
「大丈夫か?」
物憂げな土方の声が千鶴に聞いた。
「だいぶうなされてたようだが。」
土方の言葉に、千鶴の脳裏に先程までの映像が蘇った。
目の前には土方が、やっぱり心配そうに千鶴を見ている。
大丈夫だ、と言うように土方は
千鶴の背中を優しく摩り、腕の力をほんの少し強くした。
その感覚と触れそうな距離にある土方の顔に、
今自分が土方の腕の中にいることを漸く認識した。
「歳三さん、ですよね…?」
確かめるように問われた言葉に、土方は片眉を下げて笑う。
柔らかく。
「おい、他の誰かに見えるってか?」
口調は優しくても、からかうような言葉。
いつもと同じ何も変わらない土方の様子と、 すぐ近くから伝わる一番大好きな温もりに、千鶴は安堵した。
身体から力が抜けていって、土方の着物をギュッと掴んだ。
ぽろぽろと涙がこぼれ落ちる。
土方がその頬へ手を添えて、止まらない涙を受け止めた。
「千鶴?」
「すいません…。」
千鶴は謝りながら、泣き止もうと――涙を止めようと、顔を覆おうとした。
土方はその手を取ると、自分の胸元へと千鶴の顔を押し付ける。
「なにも謝る必要も我慢する必要もねえんだ。
いつも言ってるだろう、遠慮せずに甘えろ、と。」
しっかり千鶴の頭を捉え、まるで千鶴が泣くのを促すように、髪を梳く。
「悪い夢でも見たか?」
優しく紡がれていく声に、小さく頷いた千鶴の肩が震え出した。
「みんないなくなってしまうんです。
歳三さんもいなくなって、私一人暗闇の中
花が終わって葉がつかない桜の木とたった一つの花片だけ――……」
千鶴は、見た夢を土方に話した。
「最後は私独りになるんです……!」
手が白くなるくらい千鶴は、土方の着物を握り締めた。
土方の表情が微かに歪む。
自分は千鶴より先に逝くだろう
ただでさえ、激しい戦いの中に身を置いてきた。
さらに羅刹として命すら削った。
いつ寿命が尽きてもおかしくないのは間違いなかった。
だが、
と、土方は真剣な面持ちになり、千鶴にそっと話し出した。
「千鶴、確かに俺はおまえを残して逝くことになるだろう。
だがな、俺は今、千鶴の傍にいる。千鶴と共に生きている。違うか?」
腕の中で、千鶴が首を振る。
「俺はな、千鶴。
この命がある限り、生きている限り、
おまえの傍から離れねえし、離れるつもりもねえんだ。
残った命を惚れた女の為だけに使うのも悪くない、
前にそう言ったのを覚えてるか?」
今度は頷いた。
「俺はそのつもりでおまえと生きてるんだ。
そこまで惚れた女を俺が手放せるわけねえだろうが。
千鶴がいなくなるのが怖いのは俺も同じなんだよ。」
紡がれた言葉は、自然と千鶴を落ち着かせていた。
震えが小さくなった千鶴が、身じろぎし、腕の中から顔半分土方を見上げる。
まだその目は涙に濡れていた。
「だから安心しろ。」
温かな愛情満ちた笑みで、千鶴を見つめた。
「俺はおまえの傍にいる。離さねえ。これからも、な。
もしかすると、死んだ後も未練たっぷりでおまえの傍を離れられねえと思うな。」
暗い話題になりかねない後半の話題を、
おどけた口調と声で言った土方に、千鶴はやっと笑顔を覗かせた。
「歳三さんならそんな気がします。」
「言ってくれる。」
「歳三さん、ずっとずっと傍にいてくださいね…。」
もう置いて行かないで下さい
言葉の裏に篭った言葉に土方は気付いていた。
一度仙台に置き去りにした前科は、千鶴の心に深い傷を付けている。
極端に、置いて行かれること、独りになることを怖がるのは、
土方の寿命以外にこのことがあるからかもしれない。
「ああ、離さねえ。離してたまるか。」
千鶴の額に口づけながら、土方は千鶴の想いに応えた。
安堵か嬉しさか、千鶴の目から再び涙がこぼれる。
それを土方は舐めとって、流れるように千鶴の口唇に口づけた。
確かめるように、伝わるように、何度も何度も。
「千鶴、今日はこうしてしっかり抱きしめてやるから、安心して寝ろ。
また悪い夢見たら、何度でも起こして、何度でも涙拭って、
何度でもおまえが安心するまで伝えてやる。なんかあったら起こせ。」
かつて剣を握っていた無骨な手は、ただ一人愛した女の頭を撫で、安堵を誘っていた。
千鶴が眠くなってきたのか気持ち良さそうに目を細めた。
「おやすみ、千鶴。いい夢見ろよ。」
もう一度土方が額に口づけた時、千鶴は最後の雫を流して眠りに落ちた。
口唇を離した土方が、安らかになった千鶴の寝顔を見つめた。
涙を拭う。
「何があっても俺はおまえの傍にいるからな。」
桜吹雪が舞う。
気持ち良く晴れた抜けるような青空だ。
満開の桜はそんな青空によく映えた。
その木の隣、誰かと寄り添って立っていた。
温もりを直に感じれるほどの距離。
端正な顔立ちをしている。
ふわふわそよぐ風に桜の花片が舞っていた。
二人を包むように。
――歳三さん。
名前を呼ぶ。
――なんだ?
優しい声音が返ってきた。
愛おしさを込めた穏やかな微笑が見下ろしていた。
――桜、綺麗ですね。
――そうだな。
うららかな陽射しは二人が幸せだと教えてくれる。
――歳三さん。
もう一度、名前を呼んだ。
――歳三さんと一緒に見れて幸せです。
風は、二人を撫でるように過ぎていく。
風に合わせて薄紅が舞った。
ふわり。
花片は二人に降っていく。
ひとひらふたひら。
そうしてふわり。
戯れに、花片は二人を祝福する。
桜が似合うと笑い合う二人を。
――来年も……
――来年もと言わず、毎年見に来ような、一緒に。
――はい!
二人、いつまでも桜を見上げていた。
時折、お互いの視線を絡ませながら。
朝、余韻に浸りながら心地好い何かとともに意識が浮上した。
しっかりとした力強さに包まれている。
傍に、いる……
「千鶴?起きたのか?」
まだ少し眠そうな声がした。
真っ直ぐに見つめて来る視線とぶつかった。
心から落ち着くこの温もりに、まどろんでいたい、
もう少しこうしていたい、そう思ったのに。
だから、自分から身体を寄せてみる。
すると、腕に込められた力が強くなった。
「また悪い夢でも見たか?」
心配の色を含む声に、違う、と首を振って、
こうしていたいんです、と彼の背中に腕を回す。
伝わったのか、彼の雰囲気が甘く和らいだ。
「珍しいな、千鶴が甘えてくるなんて。」
嬉しそうに笑う声。
「歳三さん。」
夢と同じように名前を呼ぶ。
「なんだ?」
やっぱり夢と同じような優しい声音が返り、
愛おしさを込めた穏やかな微笑を向けられた。
急に気恥ずかしくなってしまったけれど、
なんだか目を逸らすのはもったいない気がして、その微笑を受け止めた。
「とてもいい夢を見たんです。」
それは幸せな夢を――
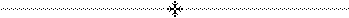
2000hitありがとうございました!!
これからもよろしくお願いします!!
フリー配布期間終了しております。

