もう何度目か、桜を共に見る日は。
寄り添い見上げていた土方は、
ふいに自分の体に違和感を感じて千鶴を掻き抱くように腕の中に閉じ込める。
瞬きの間に漆黒の髪が色素のない白髪に変わる。
驚きに目を見張っていた千鶴の目の端に、
その髪色が映り、すぐさま何が起こっているのか全てを悟った。
その瞳は、涙で溢れていた。
「なんだよ、もっとおまえと桜が見たかったって言うのによ。」
自嘲気味に口を付いて出た、切ない土方の言葉。
ふと、腕の力が緩んで、菫色から赤へと色を変えた瞳が、
悲しみと優しさと相反する感情を浮かべて千鶴を見た。
それから、自然と唇を重ねる。
短いようで長いようで、その口付けに互いの感情が余すことなく感じ取った。
「千鶴、またおまえを追いてっちまう。すまない。」
土方の無骨な手が柔らかな千鶴の頬に触れた。
「俺は、いつもおまえの傍にいる。今までと変わらない。
ずっと千鶴の隣で見守ってるから、たまには笑え。千鶴は笑った顔が一番綺麗だからな。」
もう一度重なった唇の温もりは、少しずつ消えていって、
千鶴が目を開けると、いつもと変わらず柔らかく優しく笑う土方の笑顔があった。
――千鶴、愛してるよ。
一陣の風に舞い上がった桜吹雪と共に、土方の姿は溶け込むように消えていった。
あとに残ったのは、それまで土方が来ていた紫の着物。
まだ彼の温もりが残るそれを胸にぎゅうっと抱きしめて、千鶴はかたんと膝をついた。
「私も、愛してます……!」
涙に震えた小さな声が、
風に乗って土方の後を追うように、浅葱にも似た色をした青空に消えた。
それから数日、
この間まで共に暮らしていた土方の温もりを感じ取り、涙をまた溢れさせていた。
土方の文机。
彼がそうしていたように、そこに座る。
と、正座した膝の先に何かが当たる感触に気が付いた。
少しその場所をずらし、奥の方に手を伸ばせば、硬いものが指先に触れる。
どうにか取り出したらそれは、漆黒に桜模様の入った文箱だった。
ここにあるということは土方のものだろうが、千鶴は一度もそれを見たことがなかった。
何かに導かれるように、そっと蓋を開ければ
【千鶴様】
宛名で書かれたその名前は、間違えようもない流麗な土方の文字。
自分の宛名がある文を手に取った。
【拝啓、千鶴様】
まるで直接土方に言われてるように、土方の声が低く優しく響く。
そう書き出されたその文は、土方から千鶴に書かれた初めての恋文だった。
いつ書かれたものだろう、出逢いから今までのこと、
そして新しく始まった夫婦として暮らしていく未来の話が、そこに書いてある。
【……がらにもねえ言葉だが、書いておく。愛してるよ、千鶴。】
その言葉が別れ際言われた土方の最期の言葉と重なる。
続いて書かれた言葉に、土方の千鶴への気遣いと、土方の心配する想いが見えて、
ほんの少し、土方がその生涯を終えてから初めての微笑が浮かんだ。
小さく首を振って、大切に大切に文を閉じる。
溢れて溢れて敵わない涙を両手で拭って、文を文箱に戻そうとしたその時、
土方が書き残していた千鶴への恋文がそれだけではなかったことに気が付いた。
手にしていた文を傍らに置き、
同じように【千鶴様】と書かれた文を手に取れば、また、一通文が姿を現す。
一通、また一通。
小刻みに震えるその手で、土方の文に目を通していった。
飾らない土方の言葉で綴られた恋文は、何通も出てきた。
読み重ねていくと、これまで土方と共に重ねてきた
かけがえのない日々の一つ一つがありありと甦り、新たな涙を誘う。
その日その日に贈られた土方からのくすぐったい愛の言葉、
一緒に贈られた温かい落ち着く温もりまで。
読んでいる間中、千鶴の涙は止まらなかった。
書かれた文は全て同じ文章で終わっていた。
【読み終わったら捨ててくれ、後には引きずるな、それが俺の願いだ】そう書かれている。
けれど、千鶴にはそれが出来なかった。
土方の命令を突っぱねて、海を越え蝦夷に渡ったように、
土方の愛情が溢れんばかりに詰まったその文を捨てるなど到底出来ないことだった。
例え、それが土方の願いであったとしても。
チリン…
最後の一通の手紙を取った時、軽やかな鈴の音が鳴ったような気がした。
文箱を覗けば、根付が入っていた。
鈴の音の正体はこの根付のようだ。
「根付…?」
そっと手に飛ばれば、また一つ耳馴染みのいい鈴の音が鳴った。
まるで土方と千鶴が二人一緒にいるかのような、桜の花と菫の花が並んだ浅葱の根付だ。
ひとまずその根付を机に置き、最後の文を読み始める。
その一通だけこれまで書かれた文とは違っていた。
【拝啓、千鶴様】
書き出しは同じ。
【きっとこの文を読んでるってことは、
俺がまたおまえを置いていき、この文箱を見つけたんだな。】
まるで、自分が近い日にこうなることを予期していたように綴られていた。
――拝啓、千鶴様
きっとこの文を読んでるってことは、
俺がまたおまえを置いていき、この文箱を見つけたんだな。
千鶴、この文が最期の文になる。
長いような短いような、おまえと暮らす日々は、
俺がこういうのもおかしいが、本当に穏やかで幸せで飽きない日々だ。
いつか【終わりが来るのが少しだけ怖くなった】そう言ったのを覚えているか?
もしかすると、もう短いかもしれない、
それをなんとなく悟った時、もっと足掻いて生き続けてえって心底思った。
それからの日々は、そんな怖さも忘れるくらい
幸せに溢れた日々だったていうのに、そう悟った瞬間すげえ怖くなったんだ。
俺らしくもねえだろ?
それだけおまえとの日々は幸せだっていうことだ。
何より怖かったのは、またおまえを一人置いていっちまうってことだ。
仙台で置いてきちまったこと、本当にすまねえと思っている。
そのことが、千鶴を深く傷つけたっていうのに、俺はまた同じ事をしようとしている。
千鶴、俺はおまえに何を残してやれただろうか。
俺は、おまえを幸せに出来ただろうか。
羅刹として身を削ったあの日々を後悔してるとは言わねえ。
いや、俺は俺の決断で羅刹になることを選んだ。
俺の意志だ。
だから、後悔なんてしてねえし、これでよかったんだと今は思う。
だが、こうも早く逝っちまうことになるのは、さすがに参った。
羅刹になった代償がこんなにも大きく跳ね返ってくるとは、さすがの俺も予想できなかったしな。
ただ、俺はそれでも精一杯足掻いて足掻いて生き抜いたと、おまえとの日々を過ごして思う。
千鶴、ありがとう。
俺は、本当に幸せで満たされた日々を最期に送ることが出来た。
全部おまえのおかげだ。
俺がもらった幸せの分、いやそれ以上に千鶴が幸せに暮らしてくれたかどうか、それが少し不安だが。
毎日の中で見るおまえの嬉しそうな笑顔は、千鶴がそうだった証拠だと勝手に思ってたが構わねえか?
この文を読んでいるなら、前に書いた文も読んでいるんだろう。
そして千鶴、おまえのことだ。
俺が書いたことなんて【そんなこと出来ません】って守らねえだろ。
なんてったって、ついてくるなって命令無視して函館まで追っかけてきたくれえだもんな。
だが、そのおかげでこうして俺は幸せな日々を送っている。
これでも感謝してるんだぜ。
出来ることなら、おまえには後にひきずってはほしくねえから、読んだなら文は全部捨ててくれ。
おまえは俺が迎えに行くまで俺の分まで生きてくれ。
泣くなとは言わねえ。千鶴はよく泣くからな。
泣いても構わねえが、笑ってくれ。
俺はおまえの笑った顔が好きなんだ。
それでも手紙は捨てらんねえってほざくなら、代わりに一緒に贈った根付を持ってろ。
この前出掛けた時に、おまえにと作ってもらった。
二つの花は俺とおまえだ。
この根付のように、俺が逝っちまっても千鶴の傍から離れたわけじゃねえ、変わらず千鶴の傍にいる。
もうおまえを直接抱きしめてやることも、直接涙を拭ってやることも出来ねえ。
でも、いつだって俺はおまえの傍で見守って、抱きしめて、涙拭ってやるから。
根付を俺だと思って、これからは生きてくれ。
そしていつかもう一度巡り合おう。
その根付は目印だ。
俺が見つけ出してやるから、その時までしっかり持ってろよ?
千鶴。
すまねえな。辛い想いをさせて。
愛してるよ。
ありがとう、俺は幸せだ――
「…うっ…!」
堪えきれなくなった嗚咽が漏れる。
手紙を置き、根付を握り締める。
慰めるように
チリン…
鈴の音が一つ鳴った。
「主人。」
千鶴が近くの店で買い物をしてる隙に、女物の装飾品を扱う店の主人を捕まえていた。
「お決まりですか?」
優しい人柄を感じ取れる笑顔で、店の主人は土方に聞いた。
「いや、そうじゃねえんだ。特別に作ってもらいてえもんがある。頼めるか?」
真剣な色だけに染まった真っ直ぐな瞳で、土方は主人に頼む。
そこにただならぬ想いを掬った主人は、柔和な笑顔そのままに頷いた。
「金子は弾む。悪いが、出来るだけ早く仕上げてほしい。」
「わかりました。」
「ありがとうございます。」
漸く息を吐き出すと、土方は丁寧に作ってほしいものを伝えた。
数日後、寸分違わず出来上がったそれを受け取った土方は、
思い描くただ一人の女を思い浮かべながら、目を細める。
「感謝します。」
珍しく深々と頭を下げた土方に、主人はただ笑顔で見守っていた。
その土方の手には、菫と桜の花が寄り添う、
浅葱の根付が可愛らしく鈴の音を鳴らし収まっていた。
チリン…
鈴の音が小さく響き、余韻を残しながら消えていく。
チリン…
動く度に揺れ、可愛らしく軽やかなその音を響かせる。
その音を聞く度、千鶴の胸の奥を、切なく締め付けていた。
涙が零れ落ちることもあった。
なのに、満たされる感情もある。
チリン…
――千鶴…
鈴の音に重なって聞こえた声に振り返った。
「ちゃんと持ってたんだな。」
「だって、約束でしたから…」
チリン…
――俺が見つけ出してやるから、その時までしっかり持ってろよ?
それは、140年と少し前、浅葱に似た空に土方が消えたあの日と同じ、桜が咲き誇った頃。
あの日土方を攫った桜吹雪は、二人を祝うように包んでいた。
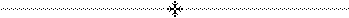
6000hitに併せて、一日早いですが、土方さんの命日に追悼の意を込めて。
2011.05.10 桜雪

