珍しく、ノックがない。
「戻りました。」
「入れ。」
いつと同じように返事をすれば、失礼しますと声が聞こえてドアが開いた音がした。
コツコツとやはり控え目な足音がする。
それは、机の近くまで近づくと、ふいに途切れた。
千鶴が何かを躊躇っている、そんな様子が伝わってきた。
多分、俺の仕事の邪魔になるのでは、と思っているんだろう。
「あの、土方さん。」
意を決したのかどこか遠慮がちに、千鶴が話し掛けてきた。
俺は、仕事の手を止めて、千鶴を見上げた。
「どう……」
どうした、という言葉は千鶴が持つものに視線を奪われ、形にならなかった。
同時に、珍しくノックがなかった理由に納得がいく。
「なんで千鶴がそんなもん持ってんだ?」
「先程大鳥さんに逢ったのですが、土方さんにって。」
途端に脱力する。
とりあえず今にも落としそうな持ち方をしている千鶴から、
琥珀色の瓶――確か【わいん】とか言ったか――とそれを飲む為の足の長いグラスを受け取った。
書類が広げてある机に置くわけにいかずに、ソファと一緒に設えてある机に避難させた。
「だからなんだってこれなんだよ。」
「なんかいいものが手に入ったんだっておっしゃってましたけど。」
ますます大鳥さんの考えがわからずため息が出た。
「ところで土方さん。」
物珍しそうに琥珀色の瓶を千鶴は眺めている。
そして、指差すと小首を傾げて聞いた。
その仕草すら可愛らしい。
「これなんですか?」
そういえば千鶴は初めてか。
「大鳥さんに聞かなかったかのか?」
「土方さんに聞けばわかるって。」
どうやら大鳥さんはこれが酒だってことを言わなかったらしい。
大鳥さんも俺が飲めないことを知っているからな。
西洋の酒が口に合わないと言うことも。
千鶴に酒だと言えば、俺のことを考えて断りそうなもんだから俺に聞けと言ったのだろう。
なかなかなことをしてくれやがる。
「これはな、確か【わいん】とかいう西洋の赤い酒だ。俺の口にはどうも合わねえ。」
苦笑いしながら答えると、千鶴は少し驚いたように目を見開き、おかしそうに笑った。
「なんだよ。」
「いえ、西洋のものはなかなか好まれませんもんね。」
以前、西洋の赤い茶が口に合わないという話をしたっけか。
わねえなあとやっぱり思いながら、その千鶴の視線が琥珀色の瓶に時折行くのが気になった。
「千鶴、もしかして気になるのか?」
「え?」
俺が聞くと、慌てて否定する。
「ちっ違います!」
本当、嘘が出来ない女だ。
違う、といっているのに視線は琥珀色の瓶に向く。
「ったく、別に怒りゃしねえよ。気になるんだろ?」
「う…」
一歩近づいて、その栗色の瞳をじっと覗いてやると、躊躇うように俺を見、口を開いた。
「気に……なり、ます。だって見たことないですし、どんなものだろうと…。」
「なら、千鶴。せっかくだ、飲んでみるか?」
「えええっい、いいです!」
驚いたのか今度は思いっきり首を振る。
「気になるんだろ?」
「ですけど...」
遠慮しているのか、千鶴はなかなか首を縦に振らない。
気になって仕方ない、というのがこちらにも伝わってくるというのに。
ならば、とソファに座り自分の隣に座れと促した。
「千鶴、こっち来い。」
「あ、はい…。」
するとこれは素直に頷いて、俺の隣にちょこんと座る。
それを確認すると、琥珀色の瓶から木の栓を抜き、二つのグラスに注いだ。
わずかに紫がかった赤い色が透明のグラスに入る。
千鶴は、その色に吸い込まれるようにして見ている。
「綺麗…。」
千鶴に、【わいん】の入ったがグラスを一つ渡す。
「土方さん?」
「随分と気になってたようだからな。」
「えっと…。」
俺が何を言わんとしているのかわかりかねているのか、再び首を傾げる。
「俺も一緒に飲むなら問題ないだろう?」
笑って言えば、微かに戸惑いの色を浮かべながらも、千鶴はそのグラスを受け取った。
「それなら…。」
「乾杯。」
千鶴のグラスに自分のグラスを合わせれば、小さく音がする。
「西洋ではこうするんだと。」
きょとん、とした千鶴をよそに、【わいん】に口をつける。
口に広がる味は、やっぱり美味しいとは俺には思えない。
大鳥さんや榎本さんは、茶もそうだが好んで口にしているようだが。
「やっぱ酒も日本のものがいいな。」
「そうなんですか?」
じっとグラスの中の【わいん】を見ていた千鶴が、
思わず顔をしかめた俺を見てそう聞いた。
「飲んでみりゃいい。」
そういえば、こいつが酒を飲んだ場面を見たことがないな。
何度か島原に連れ出したことはあったが、飲めないと言って飲まなかったような。
飲んでみろとは言った手前だが、気になった。
「ところでおまえ、酒飲めたか?」
千鶴の動きがピタリ、と止まる。
先程まで見せていた躊躇いや遠慮は、飲めないからじゃないだろうか。
「どうして…ですか?」
「いや、おまえが飲んだとこ見たことねえなと思ってよ。
思わずすすめちまったが、飲めねえものを無理して飲む必要はねえぞ。」
すると、むっと拗ねたように頬を膨らませた。
「の、飲めますよ。」
どうやら逆に煽っちまったらしい。
酔った千鶴を見てみたいという思いもある俺としては願い叶ったりなようなもんだが。
どうせこの時間に部屋にくるヤツもいねえし。
「じゃあ飲んで確かめてみりゃいい。気になるんだろ?」
「わ、わかりました。」
決意を固めた千鶴が、少々ぎこちないながらもグラスを傾け、恐る恐る口を付けた。
一口含み、小さく喉が上下する。
「どうだ?」
「よくわかりません。」
困ったように笑いながら、再び【わいん】に口を付ける。
「なんだか不思議な味がします。」
かと思えば考えるように。
コロコロと変わる千鶴の表情は見ていて飽きない。
果たして、千鶴は酔ったらどうなるのだろう。
そう考えると何だか楽しくて仕方がない。
「土方さん、どうかしましたか?」
表情に出ていたのか、訝しげに千鶴が聞いてきた。
「なんでもねえよ。ほら、飲め。」
大して減ってはいない千鶴のグラスにワインを注いだ。
それから間もなくして、だった。
「千鶴?」
微妙に千鶴を纏う雰囲気が変わったことに気付いて声を掛ければ、
「はい?」
千鶴はちょっと怪しくなった呂律と、とろんとした眼差しで見つめ返してきた。
その姿に思わず心臓が跳ねたのがわかった。
その頬は、酔いのせいか仄かに赤い。
色気というものをこれまで感じなかったわけではないが、それを確かに感じるようだ。
「もしかして酔ったか?」
その問いに、千鶴は答えなかった。
代わりに、ではないが千鶴がふにゃと笑う。
「土方さん。」
「どうした?」
聞き返してはみるものの、答えはない。
「千鶴?」
不思議に思っていると、千鶴が嬉々として抱きついてきて驚いた。
「土方さーん。」
「お、おいっ!」
「ふふあったかーい。」
ぎゅうっと抱きしめられる。
やっと追いついた思考で察するに、どうやら千鶴は酔っているらしい。
滅多に見られぬ甘える姿は、酔いから来ているものらしい。
「土方さんもしかして嫌でしたか?」
なんの反応も出来ずにいると、しゅんと悲しげな瞳で見上げる千鶴と出会う。
これは…思わず口の端が上がるのを抑えられない。
「だったらどうした?」
悪戯心が動く。
「それは嫌です……!」
思わず泣きそうになった顔に、結局俺が慌ててしまう。
「嫌じゃねえから泣くな。」
頭をポンポンと叩くと、にっこりと笑う。
「本当ですか?」
「当たり前だろ?」
「よかったですー。」
あまりにもその姿は可愛すぎた。
猫可愛がりしてえとつい思ってしまう。
「だったら今日はこのままお傍にいてくださいねー。」
まさに擦り寄り甘えてくる猫のようで。
ゴロゴロと喉を鳴らしているのかもしれない。
酒が入り、少し高い体温がなんだか心地いい。
普段からこれくらい甘えてくれてもいいもんだが。
「そんなに傍にいてほしいのか?」
もう少し甘える姿を見ていたい。
「はい!とっても!」
えへへと笑う千鶴の顔は緩みきっていて、
背中に回っている手は俺から離れようとはしない。
「離れませんからねー。」
少し近づいた距離、微かに酒の匂いが混じった千鶴の息がかかる。
思わずその唇に口付けたくなる。
「おう望むところだ。」
「土方さん土方さん、だったらぎゅうってして下さい。」
だからそんな瞳で見るなって。
喉元まで出かかった言葉は、今は不要かと飲み込んだ。
なんだか千鶴に翻弄させられているようで不思議だった。
要求された通り、力いっぱい抱きしめてやれば、幸せそうに千鶴は表情を崩したまま。
「土方さん。」
名前を呼ばれれば、酒のせいで潤んだ瞳に自分が映る。
「離しちゃダメですからね、絶対。」
むうと赤い頬を膨らませた千鶴に、吸い寄せられるように口付けようとした時だった。
千鶴の顔が揺れる。かと思えば、俺の胸の中に埋もれていった。
「千鶴?」
顔を覗き込めば、小さく規則正しい寝息が聞こえてくる。
「寝ちまったか。」
知らず知らずと舌打ちしちまった自分に、なにやってんだと苦笑いした。
ちょっと残念な気もするが。
千鶴に甘えられた記憶は殆どない。
これは大鳥さんに感謝しなければな、癪だが。
そうか、千鶴は酔うと甘えてくるのか。
ニヤリと笑みが零れてしまう。
「だが、他の野郎の前では見せらんねえなぁ。」
見せてたまるか、こんなに可愛い姿を。
果たして、明日朝今夜のこのことを覚えているのだろうか。
覚えてても覚えてなくても構わねえが、一応忠告はしておかないとな。
「他のやつの前で酒は飲むなよ?」
そして、あんな態度は取るなと。
今はすやすや眠りに付く千鶴は、さっきまでとは違った意味で可愛らしい。
今度酒飲む時は、戦いが明けてからにでもするか。
千鶴が思い切り甘えられるように。
俺が存分に甘やかせられるように。
その時は、今はまだ伝えられずにいる想いを伝えられたらどれだけいいだろう。
「ったく、あんな姿見て正気でいられるかっての。」
機嫌よく俺に甘えてきた千鶴を思い出す。
よく襲わずにいられたよな。
「寝るか。」
相も変わらず千鶴の手は俺の背中に回ったままだった。
離すのはもったいない。
あれだけ離さないでと甘えられたんだ。
離せるわけねえよな。
そっと華奢な体を抱き上げた。
翌朝、千鶴が覚えていたかどうかは土方だけが知るところ。
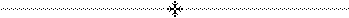
久佐様より「酔っ払って土方に甘える千鶴(時期はいつでも)」
この度は企画参加・リクエスト本当にありがとうございました!
ご期待に応えられたでしょうか…?少しでも感謝の気持ちになれば、と思います。
土方さんが酔うネタは考えていたのですが、千鶴ちゃんはまだだったので嬉しかったです。
うまく千鶴ちゃんを土方さんに甘えさせられたかどうかが不安ですが…どうでしょう…?(怖々)
もうちょっと文章力があれが土方さんの感情の揺れが掛ければと…泣。
こんなお話になってすいません。駄文でよろしければお持ち帰りいただけたら幸いです。
感想や苦情いただけたらと思います。というか、書き直しいつでも受けますのでおしゃってください!
また、お暇なときにでも、サイトに来ていただけたらと思います。

