「歳三さん――。」
自然と零れたのは今はなき愛しい人の名前。
ざぁっと吹いた一陣の風が、上も下も桜の花弁が視界を覆わんとばかりに空に舞う。
手が伸びる。
求めて浅葱の空に。
やっと貴方がいない生活に落ち着いたというのに。
泣かないでいられるようにったのに。
どうしても貴方を恋しく思うの……。
――桜の花を目にしたら
桜舞うこの季節貴方は逝った。
だから。
手を当然の如く空を切った。
と、その時。
目元の涙が拭われた、ような気がした――…。
「千鶴。」
千鶴は呼ばれた声にハッと我に返った。
「突然惚けたように泣き出すもんだからびっくりしたじゃねえか。」
「すいません。」
「どうせ、昔のことでも思い出してたんだろ。」
もう一度土方の親指が千鶴の目の淵をなぞる。
零れ落ちる前の涙が土方の手に移った。
二人には前世の記憶があった。
140年以上も前のこと。
儚くも幸せだった日々。
そしてやがて訪れた土方の死。
残されてからの日々。
今日は、昔の二人が別たれた日だった。
遅咲きの桜が咲く場所に来たのも何かのめぐり合わせだったかもしれない。
「唐突に思い出してしまって。」
「それだけお前には寂しい想いさせちまったんだな。」
切なく詫びるように気遣ように言う土方は
隣で同じように佇む千鶴を抱き寄せた。
「いえ。私もわかっていたことですから。」
それでも土方は――昔の土方は特に――大切な人に残される痛みを知っていた。
現に、遠い昔といえど土方が死にいき
千鶴がどんな想いで過ごしてきた目にしていてる。
だが、と土方は思う。
千鶴の頬をを両手で包み、大きな目をしっかり見据えて穏やかに笑った。
「安心しろ、現在(いま)、俺は生きている。」
千鶴の瞳が、俄か更に大きく見開かれた。
「そしてお前をこうして抱き寄せている。」
みるみるうちに千鶴の目に涙が溢れて頬を伝った。
「今でもあの日のことを偲んでくれるのはありがてえよ?
だがな、千鶴。俺は昔以上にお前を幸せにしてえと思ってるし
昔みたいにお前の傍を離れるつもりはねえんだ。」
頬に添えられたまま、溢れる千鶴の涙を受け止める。
「それに、だ。」
苦笑したように土方が笑う。
「あんまり昔思い出してると、俺は
昔の俺にまで妬かなきゃならなくなっちまうだろう。」
揶揄するような口調だが、千鶴には
既に土方が昔の土方に妬いてるだろうことは察しがついた。
土方自身なのに。
「昔のことですよ?」
「さっき完全に置いてけぼりだったぞ?」
「すいません。」
それから一拍置いて千鶴が言った。
「でも、今日だけは忍ばせてください。」
土方の背に腕を回し力を込めた。
「私にとって大切な日ですから。」
――空はあの色に似ていた。
今でも交わした約束を覚えている。
「俺は先に逝く。でもな千鶴。必ず巡り合おう。
その時はもうお前を離しはしねえから覚悟しとけよ。」
腕の中で聞いた、最期の約束。
「約束叶えてくれたんですね。」
「当たり前だ。」
澄んだ空に桜の花びらが舞った。
「歳三さん。」
「やっと呼んでくれたじゃねえか。」
「照れ臭くって…。あの、ありがとうございます。」
函館の今も残る桜の苑。
変わらない面影残る風景に、あの日の二人が幸せそうに微笑んでいた。
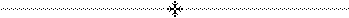
土方追悼に寄せて 2012.05.11

