なんだろうと取り出してみれば、とても懐かしいもので、思わず笑顔になってしまう。
細かい彫りの飾りは、桜の花。
片手にちょこんと乗る小さなものだけど、私にとってはとてもとても大切なもの。
ずっと使う機会もなくて、もったいなくてなかなか使えなくて。
そっと蓋を開ければ、あの日からまったく変わらない薄紅色の桜のような色をした紅。
あの頃はまだ、こんな風に一緒に暮らせる日が来るとは夢にも思わなかった。
今思えば、仄かに想いを寄せ始めていたんだ思う。
剣を向けられた最初は綺麗な人だと思った。
新選組の為に鬼になった人だったから、怖いと思っていたのに、いつからか本当はとても優しい人なのだと知り。
広い背中を追いかけるようになって、自然と目で追って、気付けば彼の傍で何か役に立ちたいと思っていた。
まだ京の屯所に居た頃、日課になっていた彼のお茶を部屋に運んだ時。
「千鶴、ちょっと付き合え。」
てっきりこの日も部屋に篭ってお仕事をされるのだと思っていた私は、
お茶を飲み終えた土方さんの一言にすぐには反応出来なかった。
「え?」
「出掛ける。だからおまえも来い。」
やっと把握した時には土方さんは既に腰を浮かしていた。
「いいんですか?」
「じゃなきゃ声かけねえよ。」
むっと眉間の皺は寄ったままで、咄嗟に体は緊張してしまったけれど、
つまり、仕事であっても土方さんと外に出れるわけで。
純粋に嬉しかった。
「あっじゃあ急いでこれ、片付けてきますね!」
緩む頬は抑え切れなくて、きっと私は満面の笑顔だったに違いない。
土方さんが小さく息を吐き、苦笑したように笑った。
「急ぎの用じゃねえんだ。急いで転んだりするなよ。」
ぽんっと大きな手が頭に置かれて、離れていく。
表で待ってると言い置いて、土方さんは先に歩き出した。
土方さんにそうは言われても、自分の中で待ちきれないように何かが急かしているようで。
「大丈夫ですよ。」
距離が出来始めた背中に、子供扱いしないでくださいと
少しむくれて声をかけ、パタパタと勝手場に急いだ。
「今日はどのようなご用事ですか?」
いつもみたいに土方さんから離れないようにと急ぎ足で歩く速度が、
今日は妙にゆっくりで歩きやすく、土方さんが合わせてくれているのだとわかった。
急ぎではないと言っていたし、何か大事な用件というわけでもないみたい。
どこか浮かない顔をして、眉間に軽く皺が寄っている横顔を見上げる限り、
あまりいい用件ではないのかもしれない。
訪れる沈黙に慣れず、そう問いかけてみれば、より一層土方さんの表情が曇った気がした。
「買い物を、な。」
土方さんには珍しく、言いにくそうに私の質問に答えた。
「買い物、ですか?」
「ああ。」
どうも言いにくそうにしている土方さんに、私は首を傾げるしかない。
すると、はぁとため息を吐いて、話してくれた。
「俺に姉がいるって話したことあったか?」
「いえ…。でも、少し前に、近藤さんからお姉さんがいるってことだけは聞いたことがあります。」
「そうか。俺は両親を早くに亡くしたから、姉が面倒見ててくれてな。そのせいか頭が上がらなくてよ。」
そう話す土方さんは、困ったよう笑いながら、
なのに、懐かしそうに目を細めていて、とても優しい横顔をしていた。
「京に来てからも何かと世話してくれたんだ。先日文が来たのはいいんだが、
これだけ世話してやったのに京土産のひとつも寄越さないのかと叱られちまったんだよ。」
「じゃあ、お姉さんへのお土産を買いに?」
「女物の装飾品やらを扱う店に男一人じゃ入りにくいし、こういうのは女と一緒の方がいいからな。」
女と一緒の方がいい、ただその言葉が嬉しくて。
土方さんだったら他にも沢山女の人がいるだろうに、私を誘ってくれた。
「この店なんか良さそうだ。」
土方さんは一軒の店の前に立つと、店の中に入っていった。
慌てて私も後を追う。
中に入れば、可愛らしい櫛や簪、手鏡などの装飾品、紅や白粉といった化粧品まで置いてある。
思わずあちこちきょろきょろと見回してしまう。
近いところで土方さんが笑っている声がした。
土方さんのお姉さんへのお土産を見に来たのに私ったら。
「すいません。」
「いや、構わねえよ。なんかいいのがあったら教えてくれ。」
「はい!お姉さん、どんな方か聞いてもいいですか?」
そうして時間をかけて土方さんとお姉さんに送る髪飾りを選んだ。
「おまえのおかげでいいもんが選べたぜ。」
ほっとしたような笑顔を見せてくれた。
「そうだ、おまえなんかほしいもんあったか?」
まったく予想が出来なかった突然の一言に、私はぽかんと言葉をすぐに口に出来ない。
「へ?」
「【へ?】じゃねえよ、今日の礼だ、なんか買ってやるって言ってんだよ。」
そこまで言われて漸くわかった。
土方さんに何か買ってもらうなんて、なんだか申し訳なく思えて、私には勿体無い気がした。
それに、ただ一緒にお姉さんへのお土産を選んだだけだ、大したことはしていないのに。
「いいえ!お気持ちだけで十分です!」
「遠慮する必要はねえぞ?こういう時じゃねえと来れねえだろうが。」
「ですが、お礼いただくほどのことはしてないですし。」
「俺がしてえんだよ。」
「でも!」
だからってはいそうですか、とは言えない。
土方さんは今日何度目かのため息を肩をすくめるようにつくと、これまた呆れたように笑う。
どうしよう、今日は沢山土方さんの見たことがない表情が見れた気がする。
「おまえも江戸の女らしく曲げねえな。だからってこのまま俺も下がれねえんだ。」
「それは私にどうしろと。」
「何かお礼させてくれ。なんでもいい、今日はおまえのわがままに付き合うさ。」
土方さんはそう言ってくれた。
土方さんの好意は嬉しい。いやだから断ってるんじゃないのだ。
だから、少し考えて、このお店に来るまでに通ったお茶屋さんを思い出した。
見たことあるお茶屋さんは、確か前にお千ちゃんが美味しいよって連れて行ってくれたところだ。
土方さんとお茶屋さんってなかなか結びつかないけど。
「じゃあここに来る時にあったお茶屋さんでお団子食べたいです。」
私が希望を口にすると、土方さんは目を見開いて驚いた。
「そんなことでいいのか?」
「はい!」
「なら、ちょっと待ってろ。包んでもらってくる。」
そう言うと土方さんは、お店の奥へと入っていった。
土方さんとお茶屋にいる。
ただそれだけなのに、非日常的に思えてしまうのはなんでだろう?
「本当によかったのか?」
あれから何度目のその質問。
土方さんは食べないというから、私は二人分のお団子をいただいた。
外に出て誰か、それも想いを寄せる人と食べるだけで、すっごく贅沢に思える。
だから私は笑顔で答えた。
「はい!十分です。」
「そうか、ならよかった。」
その微笑は反則です、土方さん。
「そうだ、千鶴。手を出せ。」
「手、ですか?」
聞き返しながら両手を出すと
「ほらこれ、おまえの分。」
そう言いながら私の手に小さなものを乗せた。
自分の方へと引き寄せて見てみれば、細かい飾りは彫られた桜の花。
「これは…?」
土方さんに聞くと開けてみろと促された。
言葉のままに開けてみれば、中に現れたのは薄紅色の桜のような色をした紅。
「紅?」
「ああ。おまえはああ言ったがな。礼だ。」
言葉が出て来なかった。
一体いつ、買い求めていたのか。
もしかしてあのお店を出る前、お姉さんへのお土産を包んで貰っている時に?
「というより、それ見付けた時におまえに似合いそうだと思ってよ。
男装を強いている俺がやるのもどうかと思ったけど、いつか男装する必要がなくなった時にでもつけてくれ。」
「ありがとう…ございます。」
「おう。」
胸が一杯だった。
そして、両手で包んだそれを大事に胸の前で握り締めて、一つだけ決めたことがあった。
あれから新選組は逆に追われる身となり、
旧幕府軍として新政府軍と戦うことになり、私も土方さんの傍に控えるようついていった。
転戦に次ぐ転戦。
それでもこれだけは手放せなかった。
今、男装する必要もなくなった。
だけど、化粧することもなく、だから、紅をつける機会もなくてずっとしまったままだったんだ。
「懐かしい…。」
あれから一度もつけることがなかったなと思い、手鏡を手にした。
指先に掬って、唇に付けてみる。
不思議と馴染んで、なのに見慣れない、変な感覚。
「やっとつけてくれたんだな。」
ふと聞こえた、もう体の一部になったような大好きな声。
「あ、おかえりなさい!」
土方さんが帰ってきたことに気付かなかったなんて。
慌てて振り返ると、驚いたようにも見える柔らかな表情をする土方さんがいた。
視線が口元に行く。
暫し時が止まったように思えた。
「あの…」
口を開く前に土方さんの指が唇に触れた。
「よく似合ってる。」
最近ではよく見せてくれるようになった、優しい綺麗な笑顔を浮かべてくれた。
嬉しそう、そう感じた。
「もう持ってないかと思ったんだが、やっぱり持ってたか。」
触れていた指が離れて、握られていた手が開かれた。
優しい笑顔はバツが悪そうに苦笑するそこにあったのは、私が手にしているものと同じもの。
「散歩に出たら、前、千鶴にあげたものと同じのを偶然見かけてな。
なかなかおまえがつけてくれないから、あの混乱のでなくしちまったのかと思ってよ。」
新しく買ってきてくれた紅を台の上に置くと、また、唇に土方さんの触れたかと思えば
「綺麗になったな、おまえは。」
そう近くで囁かれて、唇が触れた。
少し角度を変えて、そっと離れていく。
土方さんの顔はまだ近い距離があって、ふと見れば熱の篭った視線と唇が目に入った。
私がつけていた、薄紅色の紅が移っている。
「土方さん、紅が、」
拭おうと手を伸ばすと、手首を捕まえられて止められた。
「気にするな。」
手が離れたと思えば、自分の指で口元を拭い、私の唇に付け直す。
「どうせすぐ取れるんだ。」
え?と思う間もなく、再び土方さんに覆われる。
今度は息継ぐ間も与えてくれない。
「ん…ふ…。」
そのまま、とん…と背に当たる。
背中に当たる感触は畳だとわかる。
押し倒されたのだ。
「また、塗ってくれ。」
唇が完全に離れてない距離で話すから、時折土方さんの吐息がかかる。
「俺だけの前でな。」
「え…?」
どういうことだろうと見上げれば
「あんなに綺麗なおまえを他の野郎共に見せたくねえんだよ。」
元より、あなた以外に見せたいと思う人はいないのです。
縋るように土方さんの背に腕を回すとしっかり抱きすくめられた。
あの時の願いは叶ったのだ。
――この紅を塗る時は土方さんの前で――
小さな紅をこの手に握り締めた時、何故かそう思ったのだから。
お題先:「群青三メートル手前」様より
淆々五題 壱) たくさんたくさん、ありがとうを 02. 「ほらこれ、おまえの分」
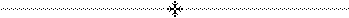
土千web企画「花誘奇録」様提出

