はじまりは、土方が千鶴にかけたその電話だった。
まだ明るい夕方、自宅まで迎えに来た土方の車に乗って走ること約1時間。
着いた先は、隣町の屋台が賑やかに並ぶ夏祭りの会場だった。
浴衣着て来い、昨日の電話でそう言われた理由を一瞬にして千鶴は納得していた。
「夏祭りですか?」
「ああ。といっても正確には花火大会だな。
なかなか逢えなかったし、花火大会行きたそうにしてたみてだし。」
「確かにそうですけど、でも私行きたいなんて一言も…。」
「おまえ見てりゃわかるさ。ここなら他のやつらに
見付かんねえだろうし、千鶴、ゆっくり楽しむとするか。」
「はい!」
千鶴は、今年買ったばかりの、白に近い淡いピンクの生地に
クリーム色の流線型の模様と色の濃い小さな桜柄がさりげなく散った、お気に入りの浴衣を着ていた。
浴衣は何故か着慣れないというより、すんなり馴染む懐かしい感覚がある。
幕末の動乱、明治へと時代が変遷するその140年以上前、土方と共に生き抜き、共に暮らした千鶴。
二人には記憶があった。
あの頃は着物も浴衣も毎日着ていたのに、そう思う千鶴だったが、
新しいものに袖を通す度、似合ってるだろうかとどう思ってくれるだろうかと、
くすぐったさと緊張とに毎回ドキドキしていたのを思い出した。
土方と、いわゆる恋人同士で、しかも土方が昔も今も
初めての恋である千鶴にとっては、好きな人に浴衣姿を見せるのは初めてで。
だから好きな人とこういった場に行くのも初めてで。
やっぱりいつもより早い鼓動に、そっと胸に手を当てて、土方にわからないようにと小さく深呼吸を一つ。
「どうした?」
わからないようにとしたつもりが、土方にはお見通しだったらしい。
「いえ、なんでもありませ…。」
なんでもないと土方を向いたところで、千鶴の語尾が消えた。
隣に並んで土方を見て、初めて土方も浴衣を着ていることに気が付いたのだ。
濃紺の無地の浴衣。
昔の土方の姿と重なり、だけど、漸く気付いたかと
苦笑にも似た笑みを浮かべた土方に、千鶴は見惚れたかのように言葉をなくす。
「昔みたいだな。」
そんな千鶴に、柔らかく笑って同じ眼差しで見下ろして穏やかな声音で言う。
「本当にあの頃に帰った気分です。」
土方の笑顔や眼差しに微かに頬を染めながら、千鶴はふわりと笑った。
短かったけど幸せの日々。
今も幸せだといえる。
「浴衣、似合ってるな。綺麗だ。」
突然顔を近づけられ、思わず体を強張らせた千鶴の耳元で囁けば、
瞬く間に耳まで夜目にもわかるほど赤く染めた。
土方が離れる際
「土方先生もかっこいいです…。」
聞こえた小さな声に、土方の動きが不意打ちされたように一瞬止まる。
少し照れたようにしたのを隠すかのように土方は千鶴の手を取り、会場へと歩き出した。
「行くぞ。」
「はい!」
人ごみに押されるように、はぐれないように手をしっかり握り返して千鶴と土方は歩き出した。
触れるほど近い距離を歩いたのは、今の時代になって初めてかもしれない。
土方の手に導かれるように歩いていった先、ふと人ごみ途切れたところに出た。
そこで土方は足を止める。
目の前は遮るものはなく、土方によるとここからが一番よく見えるらしい。
「そろそろだ。」
土方の声に重なって、花火大会開始のアナウンスがする。
ヒュー…と花火が上がる音、半拍置いてドンッと音が轟いて夜の空に光の花が咲く。
一瞬音に体を竦めた千鶴の顔に、花火のように笑顔が広がっていく。
横で見ていた土方も優しく微笑みを浮かべた。
幸せだったけど、来年は一緒に見れるかと小さな不安を
燻らせながら見ていた昔とは違い、今はただ、幸せだとただその想いだけに心ごと委ねて、
愛しい存在を確かに感じて、上がる花火に目を細める。
言葉はいらなかった。
繋がった手は強く、どちらからともなく肩を
触れ合わせるように距離を縮めて、千鶴が土方の肩に頭を預ける。
「また土方先生と見れて嬉しいです。そして凄く幸せです。」
「俺もだ。」
来年も再来年も、生きている限りずっと。
こうして二人で花火を見上げる姿が自然と思い描かれる。
「来年来る時には俺が浴衣を見立ててやるよ。」
「ふふ、楽しみにしてます。」
幸せそうな二人を、夏の光が綺麗に照らしていた。
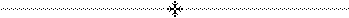
莉久様より「転生で花火大会デート」「千鶴ちゃんに桜柄の浴衣」
この度は企画参加・リクエスト本当にありがとうございました!
ご期待に応えられたでしょうか…?少しでも感謝の気持ちになれば、と思います。
わかりにくいですがSSL設定になっています。
こんなお話になってすいません。駄文でよろしければお持ち帰りいただけたら幸いです。
感想や苦情いただけたらと思います。というか、書き直しいつでも受けますのでおしゃってください!
また、お暇なときにでも、サイトに来ていただけたらと思います。

