その理由はとても簡単だ。
窓の外は、視界が遮られるくらいの吹雪になっている。
まるで今の俺の感情のようだ。
怒鳴って、暴れて、叫びたい感情を、俺の変わりに蝦夷の地が代弁しているようだ。
今夜の蝦夷は、大荒れの天気になっていた。
こんな夜は部屋でじっとしているか、酒を飲んで過ごしている者が大半だろう。
俺のように仕事をしている者はいない筈だ。
「島田さん。お疲れ様です」
「ああ雪村君。遅くまでご苦労様です」
「会議終ったんですね」
「ええ・・・」
夕方から夜遅くまで幹部達で、これからの作戦会議をしていたのだ。
敵の情報や、戦略、数など、長時間に亘り話し合っていたのだった。
「それで、土方さんはどちらにいらっしゃいますか?」
「それが・・・・」
島田は言いにくそうな顔で、土方の私室のほうに目線を向ける。
「『また』ですか?」
「ええ。『また』なんです・・・」
『また』と言うのは、以前も会議の後、機嫌が悪い土方さんは私室に篭ってしまったのだ。
そんな時は、自分の苛立ちを他人に当てたくないと、土方さんなりの優しさなのですが、
見ているこっちが心配してしまうのを、あの人は解っていないのだ。
「夕餉は皆さん食べられたのでしょうか?」
「俺達は軽くお握りなどを食べたのですが・・・」
「土方さんは食べていない。と?」
「はあ・・・食欲はないと言っておられて」
千鶴と島田は心配そうに、土方の部屋の方に視線を向けた。
「では私が後から土方さんの様子を見てきます」
「でも副長の機嫌が・・・」
「大丈夫です。叱られるのは慣れていますから」
怒られると言っているのに、千鶴ははにかむ様に笑うと
『失礼します』と言って、土方の部屋とは反対方向に向ってその場を後にしたのだった。
「相馬君」
「はい」
島田が名前を呼ぶと、何処からか隊士が現れた。
「解っていると思うが・・・」
「はい。雪村先輩の邪魔が入らないように見張っていますのでご安心を」
「ああ。頼んだよ。」
「頼まれました!」
相馬はそう言って、千鶴の向った方に急いで駆けていったのだった。
「副長、正直貴方が羨ましい。雪村君のはとても美味しいですからね・・・」
島田は千鶴たちが向った方に目を向けると、お腹がグ〜と鳴った。
千鶴が向った先は、十中八九台所だろう。
「ああ〜私の夕餉は深夜になりそうですね」
お腹を押さえながら、島田は自室に向っていったのだった。
部屋の灯りを全て消して、今は暖炉の火だけ付けてある。
その火さえ節約の為に、ほんの僅かしか付けていない。
室内は当然火の気がないためにとても寒いが、今はそれで十分だ。
土方は椅子に寄りかかるように座り、
目を閉じて、暖炉の中で薪が爆ぜるパチパチと言う音を静かに聞いていた。
トントン
誰かが扉を叩いて入室の合図をしたが、それを無視しておく。
しかしまたトントンと言う音が聞こえ、苛立ちながら扉に目を向けると、
勝手に戸を開いて入ってきた人物が目に映った。
「失礼します・・・って!土方さん。灯りもつけないで・・・」
「俺は入室の許可は出してないぞ」
「知っています。許可が下りるのを待ってたら朝になってしまいます」
「・・・・何の用だ」
「これを・・・」
そう言って目の前の机の上に置いてきたのは、ホカホカと湯気が立っている鍋だった。
「・・・島田から聞かなかったか?食欲なんかねぇよ」
「ですが召し上がったほうが良いですよ?」
土方が苛立っているのが解るが、こればっかりは引き下がれない。
「食べていただけないのでしたら、これは捨ててしまう事になります」
「・・・・」
「よろしいんですね?」
「・・・わかった」
ようやく観念した土方ににっこりと微笑んで食事をするように促す。
鍋のふたを開け小さい器によそって手渡す。
「どうぞ」
「ああ」
土方が鍋を口にすると、驚いたように目を見開いて千鶴を見た。
「この味付けは・・・」
「はい。江戸の味付けにしました」
「いや、そうじゃなくて・・・・」
手元の器をじっと見つめる。
そうだ。この味付けは、江戸で総司と最後に食った鍋と同じ味付けだ。
此処に鼈がないので、おそらく魚で出汁をとったに違いないが、
あの時食べた鍋と似たような味付けがされていた。
「懐かしいな・・・」
「・・・あの時沖田さんに言われたんです。傍にいる間だけでも土方さんの話聞いてあげて欲しいって」
「あいつがそんな事を・・・」
「ですから、愚痴でも何でも私に言ってください。確かに私は何の力もありません。ですが、話を聞くことくらいは出来ます」
「まったく、お前って奴は・・・」
(いつの間にこんなに強い女になっていたんだろう・・・)
先ほどまで土方の中で棘のように苛立っていた感情が、
千鶴と一緒にいるだけで、綺麗に融けてなくなっていく。
「沢山食べて元気出してください」
「は?」
「人ってお腹がすくと、ちょっとしたことでイラついたり落ち込んでしまったりするんです」
「そんな事は・・・」
「あるんです」
千鶴は土方の否定の言葉を遮って、拳を握りながら強く力説した。
その表情が意外に面白くて、噴出しそうになるが必死で耐えていた、
千鶴はそれが面白くなかったらしく、膨れっ面になって土方を上目遣いに睨む。
それがまた面白い顔なので、土方は堪えきれずに笑ってしまって、
千鶴も土方に釣られててクスクスと笑い、暫らくの間、二人は顔を見合わせて笑っていた。
そんな時ふと土方が窓の外を見ると、先ほどまで吹雪いていた筈の天気が、
すっかり止んでいて、おまけに丸い月まで出ている。
「本当に俺の感情と一緒だな・・・」
「え?」
「何でもねぇよ」
二人がいる暗く寒かった筈の室内は、今は月明かりに優しくて照らされて、
千鶴と千鶴の料理に、身体だけではなく、心まで温められていたのだった。
おまけ
トントン
「はい」
「あの〜島田さん。これ先輩が皆でって・・・」
「相馬君・・・これは?」
「先輩が新選組の皆の分も作ってくれたんです」
相馬が持ってきたのは、何処からどう見ても鍋だった。
「・・・・雪村君に見つかったのか?」
「は、はぁ・・・大鳥さんが・・・・」
「声をかけてきたのか」
「はい。それでばれてしまいまして・・・」
島田が命令したのは、千鶴に気付かれないようにの護衛だったのだが、
大鳥の介入によりばれてしまったのでは仕方がない。
「そうか、じゃあ野村君や安富君たちを呼んできてくれ。遅いが夕餉にしよう」
「大丈夫です。みんな集まっています」
島田が扉の外に視線を向けると、全員が横一列に並んでいた。
しかもその手には、小鉢や、箸、酒瓶などを持っているのだ。
「さすが新選組の皆は仕事が早いな」
「任せてください」
島田は皆を部屋の中に入るよう促して、全員で鍋を囲む。
「「「「「「いただきます」」」」」」
口にした鍋は、とても懐かしい江戸の味がして、
全員が笑いながらの夕餉という名の、ちょっとした宴会になっていった。
「桜と月に盃を」しょこら様より相互記念
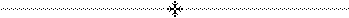
「函館時代で料理を作って土方さんを癒す千鶴ちゃん」とリクさせていただきました。
ほっとするようなほんわかするような、とても可愛らしい素敵な小説をいただきました!強気な千鶴ちゃんがいいですよね。
この度は、このようなサイトと相互していただき、またこのんな素敵なSSを書いていただき本当にありがとうございました!!
これからもよろしくお願いします!
しょこら様のサイト「桜と月に盃を」には、他にも沢山の素敵な作品が掲載されています。
もし行かれる際には、マナーをお守りの上、こちらの
 から遊びにいかれてください。
から遊びにいかれてください。
